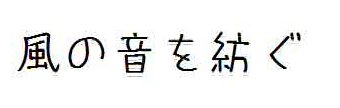春を悼む
お彼岸の頃になると思い出す人がいます。
小学校5年・6年生の担任だった先生のこと。
20年ぶりにお墓を訪ねてきました。
6年生の秋を過ぎた頃から先生は休みがちになり、怪我をしたとかいろいろ理由を聞かされながらも結局は卒業式に顔を見せることなく、その年の11月、わたしたちが中学1年生の秋に亡くなりました。
誰からともなく伝わってきた知らせを聞きながら、ぼんやり眺めていた学校の長い廊下をいまでも覚えています。
中学生が早退して葬儀に参列に行くことを認めなかった校長先生ともめたとかで卒業生有志でお墓参りに行くことになって、東金線の求名駅で先生の奥さんという人と待ち合わせてお墓参りに行きました。
確か教師をしていると聞いていたけれど、小柄な可愛らしい人は3歳くらいの男の子と一緒でした。
ほんとうにまだ小さくて、突然たくさんの人が来て一緒にお墓に行くのが楽しかったのか、はしゃぎながらちょこちょこ一緒に歩く。この子はお父さんがいなくなっちゃったのだなぁ…とため息がでて、でもまだ先生がお父さんだったことにぜんぜん実感が湧かない。悲しいとかショックとか言葉にできない喪失感はじめてで。
運転ができるようになって何度かお墓参りをしたのだけれど、ある時、住職さんとお話する機会があって『奥さんは再婚せず息子さんの成人を見届けて50歳で旅立った』と。
20年は長いだろうか、短いだろうか…

《広瀬 町子》
境内の枝垂れ桜 ひっそり三分咲き。

たった2年もない思い出だけど強烈!
…運動会のスナップ
小柄なのに筋肉の隆々腕をしたエネルギーの塊のような先生で、怒るときはめちゃくちゃ怖くて校庭を全員走らせたり、正座やお仕置き的なことは日常茶飯時で、今なら不適切が過ぎる昭和の先生と、くくられてしまいそうだけれど、卒業アルバムにはほぼみんな先生のことばかり細かに書いてある。
他の組で先生のことを書いてある文などなくて、それは驚くべきこと。
「掃除をサボっていると必ず見てる」
「集団責任で校庭を走らされる」
「授業中騒がしいと突然やめてしまう」
でも…
「自分たちが悪かったから怒られてもしかたない」と。
「ひどいスパルタ教師だったけれど、忘れられない先生」と卒業アルバムは語る。
自我の目覚める高学年の36人にひとりひとりに向けられた熱量、激しさを今でも懐かしむ。

3日降り続いた雨があがって青く澄んだ空には白い雲がぽかりぽかりと浮かぶ。
行く道々にはモクレンの紫がこぼれるよう、白い花は鳥が飛び立つように咲いている。
お寺の側を流れる川の土手にはツクシが顔をのぞかせて湿った土の匂いがする。

ひっそりと竹藪に囲まれていたお寺だった記憶とGoogle地図では、どうにもたどり着けない。
迷いに迷って車で何度も通り過ぎ、よくよく見てみれば竹が取り払われてしまった見覚えあるお寺がポツンとある。
道の駅でカサブランカの花とハイライトを。
お線香が半分になるくらいまでのんびり話してきました。

「ひさしぶりにみんなと懐かしい話にずいぶん花が咲きました」と報告を。お墓参りには好きだった煙草欠かせない。
先生が煙草好きだったのをわたしはなぜ知っているのだろう…昭和はやはり不思議な時代
彫刻刀で怪我をしたわたしを病院へ、そのあと家まで来てくれて母にお医者さんからの話しをして。頭を下げて謝る姿は誠実そのものだった。
めちゃくちゃ厳しかったけれど愛情深い人だったと知っていたよ。あたたかくて芯の通ったところ、わたしはとても好きでした。
頂いたボールペン 今も時々眺めてる。

あまりに若い。
驚き見つめ直す墓誌。
3月28日 3:03pm 蓮成寺

教室の机の上の勉強も大切。
それよりもまず体を動かすこと、五感を研ぎ澄ますこと、体験することで得られる楽しさは人生の喜びに通じる。
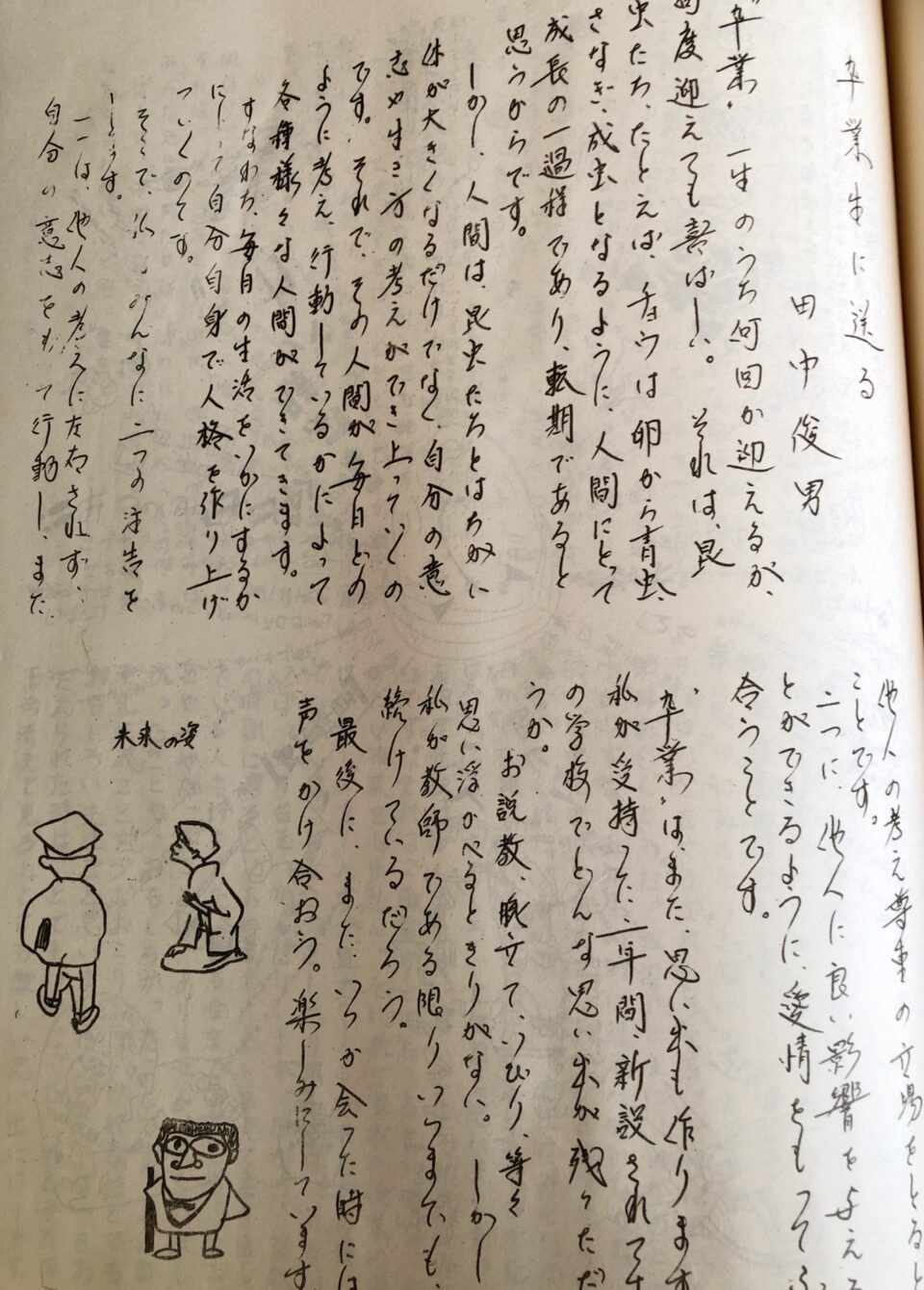
ぼくはいまでも先生のことを思うと
あのうしろ姿はあのままだれにも
呼びかえされぬままに日々に遠ざかり
豆粒になり
はるか かなたでふっと
はじけてしまったのだと思えてくる
〈辻征夫〉